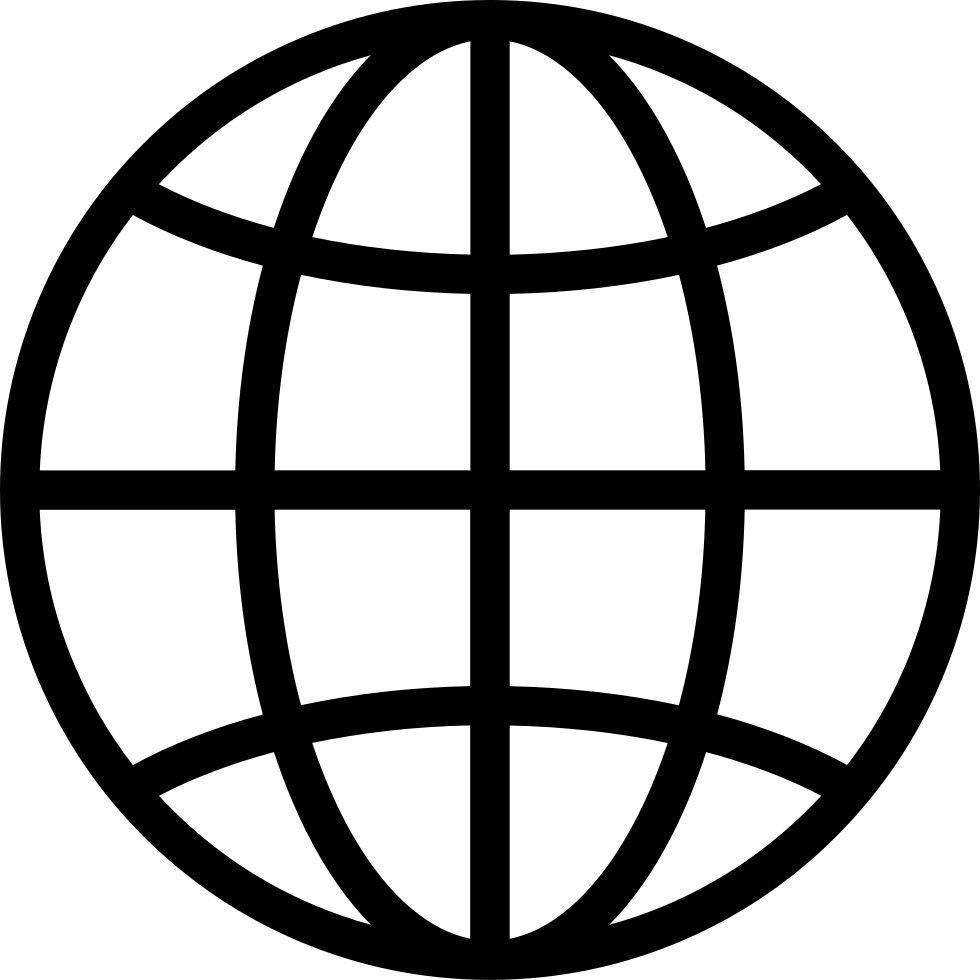Player FM 앱으로 오프라인으로 전환하세요!
デザイナーの“好奇心”を刺激するものは?|CULTIBASE Radio|Design #20
Manage episode 345484490 series 2888972
「デザイナーの“好奇心“を刺激するものは?」の概要
CULTIBASE Radioは、人やチームの創造性を高める知見を音声でお届けします。 CULTIBASE Radioデザインの20回目では、株式会社MIMIGURIのExperience Designer / Reflection Researcherである瀧知惠美と、同社のDesign Strategist / Researcherである小田裕和が、「デザイナーの“好奇心“を刺激するものは?」をテーマにディスカッションしました。
- 今回は先日小田が株式会社大広・倉田潤さんらとともに登壇したライブイベント「ブランドの『とらわれ』を脱するには?:好奇心から可能性を広げる”Brand Curiosity”の提案」でも扱った、“好奇心“というテーマについて深めていく。
- 生まれてから長い時間が経ったブランドの場合、その成功体験や固定観念から抜け出せずに停滞してしまうケースがある。イベントではそのような固定化されたブランドの意味を改めて問い直し、新たな探索を始めるために、“好奇心”をブランドに対して持つための方法論として、"Brand Curiosity"を提案し、深堀りした。
- また小田は、2021年春のドミニク・チェンさんとの対談イベントでもテーマとなった「わからなさとどう対峙するか」という問いと向き合う中でも、”好奇心”が一つ鍵になるのではないかと語る。
- 「デザイン」と「好奇心」をつなぐ概念として赤瀬川原平らによる「トマソン」と呼ばれる概念などに小田は着目し、デザイナーの好奇心を刺激する要因が何か、考えてみたいと話す。
- 仮説として小田は、些細でも違うところに目を向ける姿勢がデザイナーには備わっていることが多いのではないかと語る。特に観察の目を養うことはデザインにとっても大事であり、瀧は普段の日常の中でも何か観察する対象を決めて歩いてみるといった”遊び”が、観察を習慣化するトレーニングとしても重要ではないかと提案する。
- 観察する習慣や目、意識を養うことを心がけていくことが好奇心を育むためには効果的である。また、個人ではなくチームとしてそれぞれの見る視点の違いを楽しみながら、好奇心を育んでいくすべを見つけてみてもチームの関係性を高める上でよい取り組みになるのではないかと二人は語る。
CULTIBASE Radioは、SpotifyやApple podcast、YouTubeなどでも配信中!最新情報を見逃さないよう、ぜひお好きなメディアをフォロー/チャンネル登録してみてください!
「デザイナーの“好奇心“を刺激するものは?」の関連コンテンツ
今回の内容と関連するイベントのアーカイブ動画は下記にて公開中です。CULTIBASE Lab会員限定となりますが、現在10日間の無料キャンペーンも実施中です。このコンテンツだけ視聴して退会する形でも大丈夫ですので、関心のある方はぜひこの機会に入会をご検討ください。
▼ブランドの「とらわれ」を脱するには?:好奇心から可能性を広げる”Brand Curiosity”の提案
https://www.cultibase.jp/videos/12203
▼「わからない」を楽しむための技法:VUCA時代の探究のあり方を探る
https://www.cultibase.jp/videos/6106
◇ ◇ ◇
人と組織のポテンシャルを引き出す知見をさらに深く豊かに探究していきたいという方は、会員制オンラインプログラム「CULTIBASE Lab」がオススメです。CULTIBASE Labでは、組織の創造性を最大限に高めるファシリテーションとマネジメントの最新知見を学べる探究型学習コミュニティとして、会員限定の動画コンテンツに加え、CULTIBASEを中心的に扱う各領域の専門家をお招きした特別講座など、厳選した学習コンテンツをお届けします。
▼「CULTIBASE Lab」の詳細・お申し込みはこちら
348 에피소드
Manage episode 345484490 series 2888972
「デザイナーの“好奇心“を刺激するものは?」の概要
CULTIBASE Radioは、人やチームの創造性を高める知見を音声でお届けします。 CULTIBASE Radioデザインの20回目では、株式会社MIMIGURIのExperience Designer / Reflection Researcherである瀧知惠美と、同社のDesign Strategist / Researcherである小田裕和が、「デザイナーの“好奇心“を刺激するものは?」をテーマにディスカッションしました。
- 今回は先日小田が株式会社大広・倉田潤さんらとともに登壇したライブイベント「ブランドの『とらわれ』を脱するには?:好奇心から可能性を広げる”Brand Curiosity”の提案」でも扱った、“好奇心“というテーマについて深めていく。
- 生まれてから長い時間が経ったブランドの場合、その成功体験や固定観念から抜け出せずに停滞してしまうケースがある。イベントではそのような固定化されたブランドの意味を改めて問い直し、新たな探索を始めるために、“好奇心”をブランドに対して持つための方法論として、"Brand Curiosity"を提案し、深堀りした。
- また小田は、2021年春のドミニク・チェンさんとの対談イベントでもテーマとなった「わからなさとどう対峙するか」という問いと向き合う中でも、”好奇心”が一つ鍵になるのではないかと語る。
- 「デザイン」と「好奇心」をつなぐ概念として赤瀬川原平らによる「トマソン」と呼ばれる概念などに小田は着目し、デザイナーの好奇心を刺激する要因が何か、考えてみたいと話す。
- 仮説として小田は、些細でも違うところに目を向ける姿勢がデザイナーには備わっていることが多いのではないかと語る。特に観察の目を養うことはデザインにとっても大事であり、瀧は普段の日常の中でも何か観察する対象を決めて歩いてみるといった”遊び”が、観察を習慣化するトレーニングとしても重要ではないかと提案する。
- 観察する習慣や目、意識を養うことを心がけていくことが好奇心を育むためには効果的である。また、個人ではなくチームとしてそれぞれの見る視点の違いを楽しみながら、好奇心を育んでいくすべを見つけてみてもチームの関係性を高める上でよい取り組みになるのではないかと二人は語る。
CULTIBASE Radioは、SpotifyやApple podcast、YouTubeなどでも配信中!最新情報を見逃さないよう、ぜひお好きなメディアをフォロー/チャンネル登録してみてください!
「デザイナーの“好奇心“を刺激するものは?」の関連コンテンツ
今回の内容と関連するイベントのアーカイブ動画は下記にて公開中です。CULTIBASE Lab会員限定となりますが、現在10日間の無料キャンペーンも実施中です。このコンテンツだけ視聴して退会する形でも大丈夫ですので、関心のある方はぜひこの機会に入会をご検討ください。
▼ブランドの「とらわれ」を脱するには?:好奇心から可能性を広げる”Brand Curiosity”の提案
https://www.cultibase.jp/videos/12203
▼「わからない」を楽しむための技法:VUCA時代の探究のあり方を探る
https://www.cultibase.jp/videos/6106
◇ ◇ ◇
人と組織のポテンシャルを引き出す知見をさらに深く豊かに探究していきたいという方は、会員制オンラインプログラム「CULTIBASE Lab」がオススメです。CULTIBASE Labでは、組織の創造性を最大限に高めるファシリテーションとマネジメントの最新知見を学べる探究型学習コミュニティとして、会員限定の動画コンテンツに加え、CULTIBASEを中心的に扱う各領域の専門家をお招きした特別講座など、厳選した学習コンテンツをお届けします。
▼「CULTIBASE Lab」の詳細・お申し込みはこちら
348 에피소드
모든 에피소드
×플레이어 FM에 오신것을 환영합니다!
플레이어 FM은 웹에서 고품질 팟캐스트를 검색하여 지금 바로 즐길 수 있도록 합니다. 최고의 팟캐스트 앱이며 Android, iPhone 및 웹에서도 작동합니다. 장치 간 구독 동기화를 위해 가입하세요.